
あはきの2020年度受療率 鍼灸4.9%で低迷続く
鍼灸柔整新聞より引用

鍼灸オワコンじゃん!
これからどうしよう……
鍼灸の受療率(4.9%)をみると絶望しますよね。
さらに、日本の人口は減るばかり。
【2021年(令和3年)9月1日現在(確定値)】
総務省統計局より引用
<総人口> 1億2555万9千人で,前年同月に比べ減少
彼氏、彼女を作りたいと必死になって自分磨きをしても、出会いすらないようなものです。
とはいえ個人的には、
「鍼灸の受療率をムリに上げる必要ないんじゃないかな?」
と考えています。

受けてくれる人がいなければ、鍼灸師としての仕事がなくなるよね?
こいつバ〇じゃないの?
と思うかもしれませんが、むしろ自分達(鍼灸師)の首を絞めることになるはず。
理由は、金銭的なハードルが鍼灸師を守っていると考えているためです。
このページでは、受療率を上げるためだけに、このハードルがなくなったケースを考えてみたいと思います。
運営方針に迷っている鍼灸師の先生方にとっては、自信を取り戻すきっかけにもなるかもしれないので、サクッと目を通してみてください。
 ケニー
ケニー3分ほどで読めます。
✔記事を書いた人
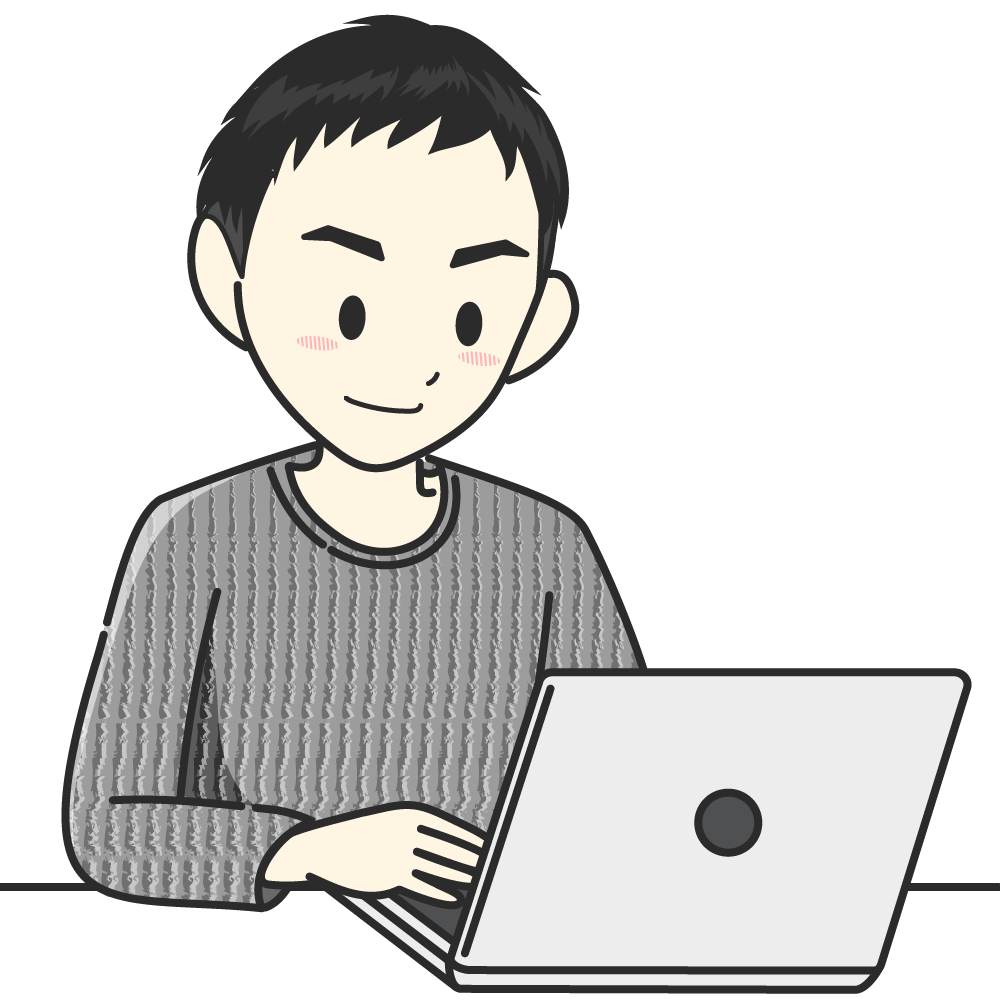
ケニー(鍼灸師&柔道整復師)
Twitterアカウント:ケニー@kenji_2nd
2019年6月に鍼灸整骨院を開業するものの6ヶ月で挫折。その後、独学でライティング&マーケティングを学び、2021年7月より治療院専門のホームページ制作を開始。kindle書籍『柔整、あはき学生が卒業前に知らなきゃ損する33の現実』『ひとり治療院むけ~廃業の足音が聞こえる15の真実~』の著者。
※無料相談や制作依頼時のメールでは、素顔を公開しています。
金銭的なハードルがなくなった鍼灸業界の未来
- 大衆化、コンビニ化で薄利多売の地獄に
- 自由に価格を決められる特権を捨てることに
- 喜ぶのは個人よりもグループ院
順番にみていきましょう。
大衆化、コンビニ化で薄利多売の地獄に

受療率を上げる=利用する人の数を増やすには、やはり大衆化が必要です。
かつて、高級料理だった寿司が大衆化したのは、回転ずしの普及がキッカケなのは耳にしたことがあるはず。
現在の鍼灸の立ち位置は、自費施術である以上、高級料理に分類されるでしょう。いっぽうで競合となりやすい保険が気軽に利用できる整骨院は、回転ずしのような扱いとなります。
✔寿司屋に例えると……
保険利用時の整骨院は
1皿120円の回転ずし

鍼灸院は
カウンターのみのすし屋

そのため、鍼灸を大衆化させるには「気軽に通える整骨院の立場」を奪う必要があります。
いいかえると、
自ら望んで薄利多売の世界に踏み込んで、ムダな価格競争に巻き込まれにいく
ともいえるでしょう。
 ケニー
ケニーとはいえ、整骨院が気軽に保険で利用できるのにはグレーな部分もありますが 笑
鍼灸院が気軽に通える価格になれば
鍼灸院を気軽に利用できるようになれば、患者層もガラリと変わる可能性もあります。
そもそもですが、多少高額でもお金を払える人は、過去にお金を払う痛みやお金を受け取る難しさを、ほかの人より多く経験している可能性が高い人達です。
いわゆるリスクを取った経験がある人ともいえますね。
しかし、世の中の大半の人は「とにかく安く、なんならタダで!」といった思考(デフレマインド)を持っています。
そのため、たとえ少額だったとしても、お金を払う場面では自分が得をしたい思いが強いため、クレームも起きやすくなると考えられます。
このあたりは、病院 or クリニック勤務をしていた方なら、想像しやすいのではないでしょうか?
大衆化すれば、いままでと利用される人の層が大きく変わる可能性は否定できません。
 ケニー
ケニー大衆化が鍼灸業界にとってプラスとなるかといわれたら、疑問が残ります。
自由に価格を決められる特権を捨てるようなモノ
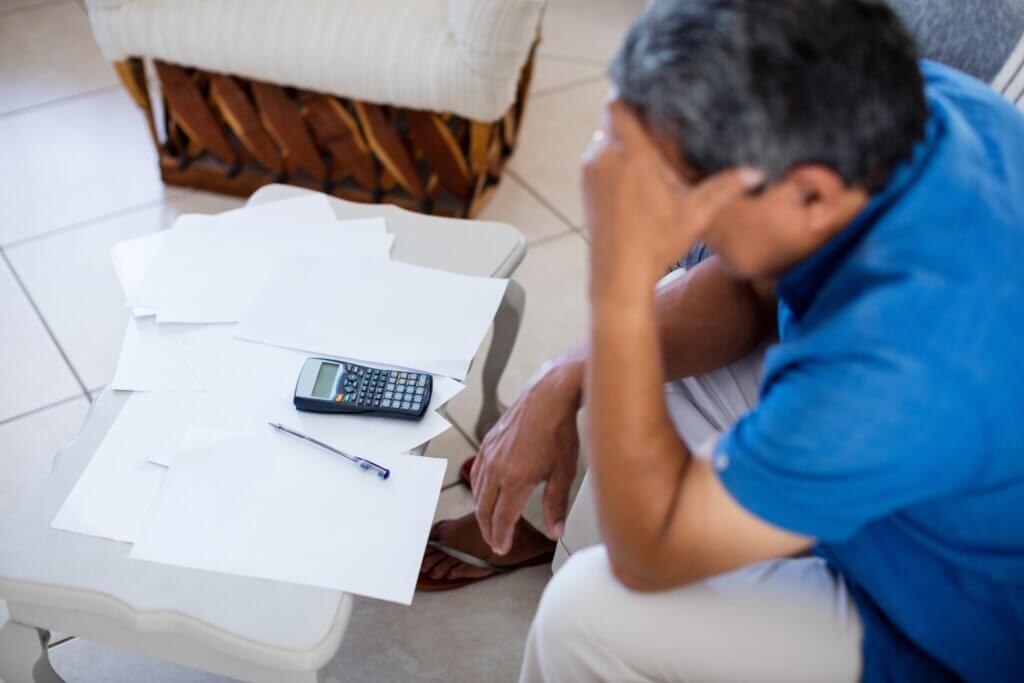
鍼灸は医療のカテゴリーにふくまれていながら、保険適用になるものはかぎられています。
保険適用の対象疾患
- 五十肩
- 頚腕症候群
- 腰痛症
- 神経痛、
- リウマチ
- 頸椎捻挫後遺症(むちうち症)
- その他痛みの整形外科疾患
医療従事者なら説明するまでもありませんが、保険を利用するならどれだけ素晴らしい技術を提供しても受け取れる金額に上限があります。
さらに、医師の同意がなければ保険適用されません。
そのため鍼灸院では、利用される方がどのような症状であったとしても、金額設定を自由にできる特権があるともいえます。
この特権を捨ててまで、まわりにあわせて大衆化、コンビニ化した料金にすれば、それこそ自分達の首をしめてしまうのではないかと。
喜ぶのは個人よりもグループ院?鍼灸が衰退するキッカケにも?

鍼灸が大衆化したら、喜ぶのは資金力がありスタッフも豊富なグループ院です。
施術内容をルーティン化すれば、回転率もあげられるためひとまず受療率をあげるのにひと役買えるでしょう。
とはいえ、そんな施術で鍼灸が本当に普及=受療率が上がるかといわれたら、むしろ衰退するのではないでしょうか?
ひとりひとりの体に合ったオーダーメイド治療を捨ててしまうのは、鍼灸施術の特徴をなくすようなものとも考えられます。
 ケニー
ケニーなんなら、高額回数券を売るだけのスタッフになるケースもありますよね……
鍼灸はナニをするかよりも『誰』がするかが重要
かなり個人的な意見ですが、鍼灸の施術は『属人性』がかなり強くないですか?
鍼灸師および、鍼灸を好んで利用している方ならわかるはず。
代替医療といいながら、よくもわるくも「代わりが効かない」ものと感じています。
そうはいっても鍼灸を受療率を上げたいよ……

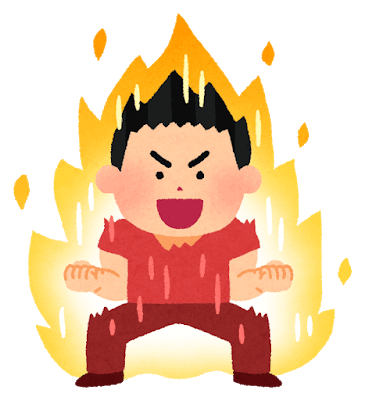
あーだこーだいっても、やっぱり鍼灸の受療率は上げたい!
ですよね。
では、どのような人に鍼灸を利用してもらったらよいのかを考えてみましょう。
個人的な意見としては
- 口コミで広めてくれる人
- 発信力のある人
- 発信を継続している人
それぞれの例をあげるなら、
- 口コミで広めてくれる人→女性
- 発信力のある人→インフルエンサー
- 発信を継続している人→Twitter運用をしているフリーランス
といった感じかと。
このなかで、いちばんとっつきやすいのは、女性をターゲットとした運営方針ではないでしょうか?
ちなみに世の中の商品やサービスの8割以上は、女性のために作られているといわれています。
女性をターゲットといっても選択肢は多い
さらに「女性」と一言でいっても、
- 美容関連
- 婦人科疾患
- 不妊
- 小児鍼
- 性にかかわる悩み
- 女性アスリート
など、求められるものは色々あります。
 ケニー
ケニー自分が「どの分野にいちばんアプローチしやすいか?」を考えてみるのもよいかと。
女性鍼灸師の活躍がカギを握る?
女性をターゲットにしつつ受療率を上げるなら、女性鍼灸師の活躍がカギと考えています。
たしかに、婦人科疾患を得意とする男性鍼灸師は数多く存在します。
とはいえ、鍼灸を受けたことのない女性としては、見ず知らずの男性にセンシティブな悩みを打ち明けられるかといわれたら……
 ケニー
ケニー正直なところ疑問が残ります。
とくに悩みが大きければ大きいほど、鍼灸という選択肢をとらないはず。
しかし、活躍している女性鍼灸師が増えて、悩みを抱える女性が気軽に相談できる環境ができたなら、すこしは未来が変わるのではないでしょうか?
本来であれば○○師会の人達がやるべきことなんですけど、頭の固いジ〇イが多いのか、あまりこのような話題を耳にしない気がします。
(知らないだけならスイマセン)
 ケニー
ケニー鍼灸を利用したい女性と女性鍼灸師だけが利用できるプラットフォームが作れたら面白いかも?
まとめ
- 大衆化で受療率が上がっても鍼灸師のメリットはすくない
- 価格を決められる特権をすてるようなもの
- 喜ぶのは個人よりもグループ院
属人性の強い鍼灸という分野だからこそ、むりに受療率にこだわる必要はないかなと考えています。
とはいえ、個人単位で見るとやはり利用する人を増やしたいのが正直なところ。
となると、活躍する女性鍼灸師が増えて、悩みを抱える女性が気軽に鍼灸を受けられる環境ができれば、自然に鍼灸が普及していくかなー、なんてことを妄想しています。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
すこし宣伝
kindle書籍では学生時代から知っておくと100万円以上得をする情報や、筆者の勤務時代~開業~廃業までをリアルに書いた内容をまとめています。
 ケニー
ケニー販売開始(2021年11月~)から現在に至るまで、毎月10冊前後はダウンロードされています。
冷やかし程度に内容をチェックされる方、は以下のリンクをご確認ください。









